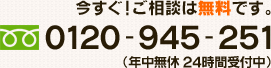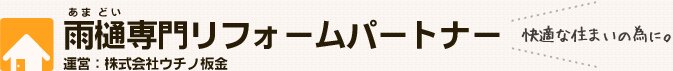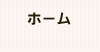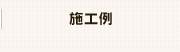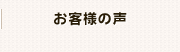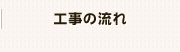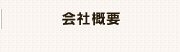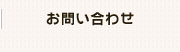雨樋に水がたまる原因とは?放置すると発生するトラブルなどを解説

「雨樋に水がたまった!放っておいても大丈夫?」
「雨樋に水がたまらないように対策をしたい」
雨樋に水がたまることで困っている人がいます。
雨樋に水がたまるトラブルは、異臭や建物の劣化といった不具合の原因になるものです。
本記事では、雨樋の役割や詰まりを放置することで起こるトラブル、対策について解説します。
雨樋費用の相場や工期の目安についても紹介しますので、雨樋修理を検討中の方の参考になれば幸いです。
雨樋に水がたまる原因

雨樋を正常に使用するためには、原因を知って対策を行うことが大切です。
原因には、大きく分けて下記のような2つがあります。
・落ち葉やゴミ、泥などの詰まり
・経年劣化による変形
・雨樋の歪みによる勾配不良
・野鳥の巣づくり
それぞれ詳しく説明します。
落ち葉やゴミ、泥などの詰まり
雨樋が水を正しく流せない主な原因は、落ち葉やゴミ、泥などが詰まることです。
特に秋になると、周囲の木々から落ち葉が雨樋に流れ込むことが多くなるので注意しましょう。
また風によって周囲のゴミや小さな枝が雨樋に飛ばされ、詰まりの原因になる場合もあるので注意が必要です。
雨が降る際に屋根から泥が流れ込むこともあり、雨樋内で固まって詰まりを形成することもあります。
経年劣化による変形
経年劣化による変形で、雨樋に水がたまるケースがあります。
長期間の使用や日焼けの影響によって変形し、正常な排水が妨げられて雨樋のつまりになります。
とくにプラスチック製の雨樋は紫外線や温度変化によって劣化しやすく、変形に注意が必要です。
雨樋の接合部が経年劣化することによって、水がうまく流れないこともあります。
水の流れが妨げられるので、経年劣化による変形がないか定期的なメンテナンスが大切です。
雨樋の歪みによる勾配不良
雨樋の歪みによる勾配不良も、雨樋に水がたまる原因の1つです。
猛烈な台風や大雪、雹など想定外の負荷を受けることで、雨樋は歪んでしまうことがあります。
雨樋が歪むと、勾配が不足したり逆勾配が発生したりするなど、不具合の原因になりかねません。
たとえば排水の流れが悪くなったり、排水管の中に排水が滞留して詰まったりする原因になります。
野鳥の巣づくり
野鳥の巣づくりが原因で雨樋に水がたまる確率が高まります。
野鳥は安全で暖かい場所に巣を作りやすいです。
雨樋は屋根の近くにあり、鳥の天敵から身を守れるため、巣づくりに適しているといえます。
屋根や外壁は熱がたまりやすいため、野鳥にとって快適な温度が保たれることも雨樋に巣を作る理由の1つです。
雨樋付近に巣づくりを始めた結果、野鳥が運んできた葉っぱや木の実、泥や巣自体が雨樋に詰まる場合もあります。
ただし住宅の敷地内にできた鳥の巣でも、駆除は勝手にできないので注意してください。
鳥獣保護法という法律により「鳥獣を捕獲・殺傷したり、鳥類の卵を採取・損傷したりすること」は、鳥獣保護法の8条で禁止されています。
違反すると、1年以下の懲役または100万円以下の罰金を請求されます。
駆除したい場合は、まずはお住まいの市町村に相談するのがおすすめです。
雨樋の役割

雨樋は屋根から降った雨水を一箇所に収集し、管や鎖を通じて排水設備に導くものです。
これによって、雨水が建物の外壁や周囲の地面に直接当たることを防ぎ、建物の損傷や劣化を予防します。
雨樋が適切に機能することで、家や建物を雨水の影響から保護してくれます。
雨樋が正しく機能するためには、適切なメンテナンスの実施が大切です。
しかし、メンテナンスができていないと雨樋に水がたまったり劣化を早めたりする原因になるので注意しましょう。
雨樋の詰まりを放置すると起こるトラブル

雨樋の詰まりに関しては、大きなトラブルが起こるまで放置する人も少なくありません。
しかし、詰まりを放置していると家屋の劣化につながることもあります。
雨樋の詰まりを放置すると起こるトラブルを4つ紹介します。
・雨樋の破損
・蚊や虫、シロアリの発生
・異臭の発生
・屋根や外壁など建物の劣化
・近隣住民との軋轢を誘発
1つずつくわしく解説します。
雨樋の破損
雨樋の詰まりを放置すると、雨樋が破損する原因になります。
雨樋が詰まると、雨水が流れずにたまり、その水の重さによって雨樋に圧力がかかります。
長時間にわたる水の重圧が雨樋の強度を超え、亀裂や破損を引き起こすことも少なくありません。
とくに紫外線による経年劣化が発生していると、雨樋の破損の原因になりやすくなります。
冬場は詰まった雨水が冷えて凍ることで、雪や氷の塊が雨樋内にできて氷が膨張します。
雨樋を圧迫し破損する原因となるので注意が必要です。
蚊や虫、シロアリの発生
詰まった雨樋に雨水がたまると水たまりができ、蚊や虫の繁殖場となる可能性が高いです。
特に蚊は水たまりで卵を産み、幼虫が発生します。
虫や蚊が増殖し、雨樋から室内に侵入してしまいます。
自宅だけではなく、周辺住民に迷惑をかけるかもしれません。
これらの外注を放置すると、生活環境の不快感や衛生面の問題を引き起こします。
蚊や虫、シロアリの発生を予防するためには、水のたまりをつくらないのはもちろん、雨樋周辺の清潔さや乾燥した状態を保つことも大切です。
異臭の発生
雨樋に詰まった汚れや水が腐敗すると、異臭の発生源となります。
詰まった雨樋内は湿度が高くなり、腐敗物が環境中で分解されるため異臭が発生します。
異臭は周囲の住宅や近隣にも拡散し、不快感や環境問題を引き起こすため気を付けなくてはいけません。
特に暖かい季節や湿度の高い気候では、この臭いがより顕著にでます。
屋根や外壁など建物の劣化
雨樋の詰まりは、屋根や外壁など建物が劣化する原因の1つです。
詰まった雨樋が雨水を適切に排水できない場合、雨水は建物の外壁内部に浸入することがあります。
外壁材が水分を吸収すると、腐食やひび割れ、塗料のはがれなどの劣化につながります。
雨樋の詰まりが建物の劣化に与えるリスクは大きく、影響が外壁や屋根に及ぶことを知っておきましょう。
近隣住民との軋轢を誘発
雨樋から落ちる雨水が、近隣住民へのトラブルを誘発する恐れがあります。
雨樋から雨水がポタポタと流れ落ち、エアコンの室外機や給湯器、物置などに当たる音は近隣住民には耳障りかもしれません。
軒下にトタン屋根があればより大きな音になり、夜中に水音が鳴り響けば、騒音トラブルに繋がる可能性が高いです。
また、はねた水が隣家の玄関や外壁などにかかったり、汚れたりすると近隣トラブルに発展するかもしれません。
雨水が流れ落ちる音や、水しぶきが近隣住民に迷惑がかかるかもしれないので注意しましょう。
雨樋修理の費用相場

雨樋修理の費用相場は、全体工事だと15~30万円ほどです。
軒樋や集水器、呼び樋などを含めた雨樋の部分修理の場合は、2〜5万円ほどが相場となります。
ただし上記の費用相場は、足場費用を除いた額です。
実際の工事では足場を設置するケースがあり、足場費用は修理費用とは別に10~30万円かかります。
そのため一般的な住宅で全雨樋の交換工事の際に足場を設置した場合は、40〜60万円が相場です。
しかし雨樋の状態や作業環境によって、相場よりも費用が高額となるケースもあります。
たとえば既存の雨樋に落ち葉よけネットがついている場合です。
落ち葉よけネットがついていると、それを外してから工事を行う必要があるため時間と手間がかかるため、別途費用が発生する可能性があります。
雨樋修理の工期の目安

雨樋修理の工期は、全体補修・交換であれば2~3日が目安となります。
修理箇所や量にもよりますが、部分交換や軽微な修理であれば工期は半日ほどです。
ただし住宅の大きさや作業環境、足場の有無によっても雨樋修理の工期は異なります。
詳細な工期を把握するためにも、契約時に工事日程を確認するのが適切です。
雨樋修理はどこに頼むのが適切か

雨樋専門業者という業者は存在しないため、雨樋の不具合はどこに相談したら良いのか悩む方も多いのではないか。
雨樋修理を依頼できる業者は、以下の4つが挙げられます。
・屋根や雨樋の修理業者
・ハウスメーカー
・工務店
・ホームセンター
予算や希望の工事内容を考慮して、自分に適した業者に依頼しましょう。
屋根や雨樋の修理業者
屋根修理を請け負っている建築板金業者や瓦業者は、基本的に雨樋修理にも対応しています。
屋根や雨樋の修理を専門としている建築板金業者などは、自社職人が在籍している業者が多いです。
自社職人が直接施工できる業者は、比較的費用が安価で柔軟な対応が可能な点が大きな魅力といえます。
そのため雨樋修理は、自社職人が在籍している建築板金業者や瓦業者への依頼がもっともおすすめです。
ハウスメーカー
家を建てた施工業者や大手ハウスメーカーは、雨樋修理を引き受けてくれます。
ただしハウスメーカーは依頼引き受けの窓口になるだけで、実際に施工するのは下請け業者や孫請け業者です。
雨樋修理は関わる業者が多いほど中間マージンが発生するため、費用が高額となります。
そのため直接施工する業者と比較すると、ハウスメーカーへの依頼は費用が高額です。
工務店
雨樋の修理は、地元の工務店にも依頼できます。
地域密着の工務店であれば、修理後も不具合が発生した場合も気軽に相談が可能です。
ただし工務店といっても様々な業者があり、自社職人が施工する場合もありますが、下請け業者が施工する場合もあります。
下請け業者が施工する場合は中間マージンが発生するため、費用が高額になりがちです。
工務店に雨樋修理を依頼する場合は、実際に施工を行うのはだれか事前に確認する必要があります。
ホームセンター
近年、大手ホームセンターでは雨樋修理の依頼を受け付けているところもあります。
ホームセンターの雨樋修理は、普段利用しているところなので安心感があり、かつ買い物ついでに依頼できる点が魅力です。
一方でホームセンターの雨樋修理は「依頼を受け付けているだけ」になるため、工事内容の摺り合わせは別途業者と相談する必要があります。
実際に施工するのは下請け業者となるため中間マージンが発生し、直接施工する業者と比較すると費用が高額になりやすいです。
気軽に修理を依頼するならホームセンターも悪くはありません。
ただ費用や手配される業者の質などを考慮すると、自分で信頼感のある業者を探して依頼した方が良いです。
雨樋の水たまりを防ぐための対策

雨樋は、視認性の低さからトラブルに気づくのが難しい箇所です。
それゆえ、事前に水たまりを防ぐための対策を実施することが大切です。
・雨水の流れを確認する
・定期的に雨樋を掃除する
・落ち葉よけネットを設置する
1つずつくわしく解説します。
雨水の流れを確認する
雨樋の水たまりを防ぐためには、雨上がりに雨水の流れを確認することがおすすめです。
雨水の流れを確認することで、雨樋が水たまりを作らずスムーズに排水できるか把握できます。
雨水の流れを確認することで、周辺環境への影響を最小限にできます。
雨が降っている時に雨樋の水の流れを確認し、適切な排水ができているかチェックしてみましょう。
定期的に雨樋を掃除する
定期的な雨樋の掃除は水たまりの発生を防ぐために重要です。
定期的な雨樋掃除を実施することにより、雨樋内部にたまった落ち葉、ゴミ、泥などの詰まりを除去できます。
水たまりの発生を防ぎ、雨樋のトラブルにも気がつきやすくなるでしょう。
定期的に雨樋を掃除することで、快適な住環境を維持し建物をよりよい状態で保てます。
落ち葉よけネットを設置する
落ち葉よけネットを設置すれば、落ち葉やゴミなどが軒樋にたまって詰まるのを防げます。
カバータイプの場合、取り付けるための専用吊り具が必要です。
落ち葉よけネットなら、雨樋の中に網状のネットを丸めて金具で留めるだけなので、簡単に設置できます。
落ち葉だけではなく、鳥が巣を作りづらくなり、枝や鳥のフンが雨樋にたまるのを予防することも可能です。
ただし落ち葉よけネットの穴は、雨水を通すためそこまで細かくありません。
広葉樹などの大きな葉っぱなどは雨樋にたまりませんが、泥や土、細い葉っぱは雨樋の中に入る可能性が高いです。
葉っぱやゴミを長年放置すると雨漏りの原因となるので、定期的な雨樋の掃除が欠かせません。
またネットのワイヤーが劣化しやすいので、周期的に交換も必要になります。
雨樋修理の費用を安く抑える方法

雨樋修理の費用は、できるだけ安く抑えたいものです。
修理費用を安く抑えるポイントは以下の3つが挙げられます。
・自社で施工を行っている業者に依頼する
・相見積もりで費用を比較する
・劣化が進行する前に修理を依頼する
できるだけ費用を抑えて適切なタイミングで修理を行いましょう。
自社で施工を行っている業者に依頼する
雨樋修理の費用を抑えたい場合は、自社で施工を行っている業者に依頼するのがおすすめです。
雨樋修理に関わらず住宅の修繕やリフォームでは、関わる業者が多いほど中間マージンを確保するため費用が高くなります。
そのため雨樋修理の契約をした会社と実際に施工する業者が異なる場合は、契約した会社が直接施工する業者と比較すると高額です。
自社職人が直接施工する業者の場合、費用が安価なだけではなく柔軟な対応が可能なため、満足度の高い雨樋修理ができます。
相見積もりで費用を比較する
雨樋修理を信頼できる業者へ依頼したい場合は、2社までを目途に相見積もりをとるのがおすすめです。
相見積もりとは、複数の業者から見積もりをとり比較する手法です。
相見積もりは費用相場の把握や担当者の人柄などを確認できるため、信頼できる業者への依頼につながります。
相見積もりでは「もっとも安価な業者」だけで選択するのではなく、この会社に任せたいと思える業者に依頼するのが適切です。
劣化が進行する前に修理を依頼する
雨樋修理の費用を抑えたい場合は、劣化が進行する前に修理を依頼するのがおすすめです。
雨樋の不具合は、放置していても自然に治ることはありません。
それどころか劣化が進行して広範囲の修理が必要となるため、費用が高額で工期も長くなります。
「雨樋の流れが少し悪いかも」「雨樋が少し歪んでるかも」など、すこしでも疑問がある場合は専門業者へ相談するのが適しています。
雨樋修理に火災保険は使えるのか

自然災害により雨樋が損傷した場合は、火災保険が適用される可能性が高いです。
火災保険は火災だけでなく風災や雹災、雪災、水災、落雷などが発生した場合にも利用できます。
雨樋の経年劣化や業者の施工ミス、被保険者の故意による損傷などは保険の対象外となるので注意してください。
自然災害が原因となる雨樋の損傷は、被害に遭った日から3年以内に申請しなければなりません。
加入中の火災保険のプランごとに自己負担額が設定されており、修理費用が自己負担額を上回らない場合は請求できない可能性もあります。
雨樋の修理に火災保険を使いたい場合は、保険会社や担当者に相談するのがおすすめです。
自分で雨樋を掃除する方法

雨樋に落ち葉やゴミをためないためには、定期的なメンテナンスが不可欠です。
参考までに、ここでは自分で雨樋を掃除する方法を紹介します。
なお雨樋掃除は高所での作業となるため、転落やケガをする恐れがあります。
素人では危険な場合も多いため、1人で作業する場合や2階建て以上の住宅の場合は、専門業者に依頼するのがおすすめです。
雨樋の掃除方法
自分で雨樋の掃除をする際に用意するものは、以下を参考にしてください。
・ホウキ
・トング
・軍手
・ゴミ入れ用の袋
・ホース
・梯子もしくは脚立
まず梯子か脚立を使い、軒樋の落ち葉や泥をトングや柄の長いホウキで取り除きましょう。
雨樋は集水器に向かって水が流れるので、集水器付近に落ち葉がたまっていることが多いです。
集水器の中は手が入らないので、トングや柄の長いホウキを使って、落ち葉や小枝を取り除きましょう。
次に落ち葉やゴミを取り除けたら、屋根と垂直に走っている縦樋にホースで水を流します。
ホースから勢いよく水を流せば、縦樋にたまっていたものを水と一緒に排出できます。
自分で雨樋掃除をする際のポイント
自分で雨樋の掃除をする際に注意したいポイントは以下のとおりです。
・必ず2人以上で掃除作業をする
・高所での作業はしない
・雨の日や屋根が濡れている場合は作業を控える
2階建以上の住宅の雨樋は高所にあるため、作業中に誤って転落する恐れがあります。
高所での作業になる場合は、必ず専門業者に頼みましょう。
1人で梯子や脚立に登るのは危険なため、1人での作業はしないでください。
不安定な場所に梯子や脚立を設置したり作業中に物が当たったりすると、梯子や脚立が倒れる可能性があります。
自分で雨樋の掃除をする場合は必ず2名体制で行い、梯子や脚立を使用する場合は1人がしっかりと支えましょう。
また雨や天候が悪いと足場の確保がきちんとできず滑りやすいので、必ず天気が良い日に作業をしてください。
業者にメンテナンスを依頼するのが適切なケース

雨樋の掃除は、素人でも可能ですが、業者にメンテナンスを依頼するのが適切なケースもあります。
下記のような場合は、板金業者に依頼するほうが安心です。
・高所での作業が必要な場合
・雨樋の状態が悪い場合
・時間や手間をかけたくない場合
雨樋修理の依頼先は「板金業者」もしくは「瓦業者」です。
1つずつ詳しく説明します。
高所での作業が必要な場合
高所での雨樋のメンテナンスは危険を伴うため、板金業者にメンテナンスを依頼するのが適切です。
屋根や高い場所に雨樋がある場合、安全な方法で作業するのは難しいものです。
板金業者は高所作業の経験があり、適切な器具や保護具を用いて作業することで適切な安全対策を取ることができます。
個人でも雨樋の掃除やメンテナンスができますが、危険です。
板金業者は適切な設備と技術を持っており、安全に高所作業を行うことができます。
雨樋の状態が悪い場合
雨樋の状態が悪い場合、メンテナンスを兼ねた板金業者へのメンテナンス依頼がおすすめです。
雨樋の状態が悪いまま放置したりなんとなくで直してしまったりすると、外壁にも悪い影響を与えてしまうことがあります。
板金業者に依頼すれば、基本的には作業の保証やアフターサービスもあり安心です。
万が一作業に問題があった場合や、後日新たなトラブルが発生した際にも、板金業者が迅速に対応してくれるため安心です。
時間や手間をかけたくない場合
自分で雨樋修理に時間や手間をかけたくない場合は板金業者に依頼しましょう。
板金業者は専門的な知識と技術を持っており、効率的かつ正確な作業を行います。
素人が自分でメンテナンスを行うときには、足場の確保や掃除道具の準備など思った以上に時間がかかるものです。
DIYで雨樋修理を試みたもののうまくいかず、結局業者に修理を依頼した、となりかねません。
不具合対応に手間取らないためにも、業者へ相談するのがおすすめです。
業者選びで注意したいこと

雨樋の掃除や修理を専門業者に依頼する際に、どのような業者に依頼すれば良いか迷うかもしれません。
業者を選ぶ際に注意したことは以下のとおりです。
・見積書の項目が詳細に記載されているか
・担当者が質問に対して誠実に答えてくれるか
・実績が豊富にあるか
それぞれの注意点を解説します。
見積書の項目が詳細に記載されているか
正式に業者に依頼する前に、見積書の内容が誰の目から見ても明朗会計かどうかを確認しましょう。
雨樋の修理費用は、業者によって料金体系が異なります。
たとえば修理範囲は雨樋全体か、または破損した箇所のみなのかで価格は違います。
また、ざっくり「一式」と記載された見積書には注意してください。
手抜き工事が行われた挙げ句「(必要だと思われる工程は)見積もりに含まれていない」と言われてしまうケースもあります。
大事な住まいの修理に後悔しないためにも、疑問や不明な点はあらかじめ業者に確認するのがおすすめです。
担当者が質問に対して誠実に答えてくれるか
担当者の対応の良さも、業者選びの際に重視したいポイントの1つです。
修理内容は専門的な内容が多いため、素人ではわかりにくいかもしれません。
質問した際に丁寧にわかりやすく回答してくれたか、親身に対応してくれたかどうかなど、問い合わせや調査時の対応がどうだったかをチェックしましょう。
業者のホームページに掲載されているお客様の声や口コミを確認して、対応を知るのもおすすめです。
実績が豊富にあるか
実績や経験が豊富な業者なら、安心して依頼できます。
依頼したい業者のホームページなどを確認して、雨樋修理に関する豊富な実績がある業者か確認してみてください。
実績以外にも「地元での評判は良いか」「何年も続いている会社か」などをチェックするのもおすすめです。
雨樋修理で業者とのトラブルを未然に防ぐポイント

雨樋修理では、まれに業者とトラブルに発展してしまう場合があります。
業者とのトラブルを未然に防ぐポイントは、以下の3つです。
・地域密着型の業者に依頼する
・詳細な見積書を出してもらう
・作業終了後は水を流してチェックする
トラブルを未然に防いで、雨樋修理を行いましょう。
地域密着型の業者に依頼する
雨樋の修理は、地域密着型の業者に依頼するのがおすすめです。
雪が降る地域や台風が多い地域など、地域ごとに適した雨樋が異なります。
雨樋は、地域の気候に適した部材を使用することで長持ちします。
逆に現地の気候と相性の悪い雨樋を使用してしまうと、早々に不具合が発生する恐れがあるのです。
地元での施工実績が豊富な業者は地域特有の気候を知り尽くしているため、長持ちする施工につながります。
詳細な見積書を出してもらう
トラブルを未然に防ぐには、詳細な見積書を出してもらうことが重要です。
雨樋工事は、修理と交換では費用が大きく異なります。
全体交換が必要か部分補修で済むのかを丁寧に診断してもらい、納得のいく見積もりを出してもらうのがおすすめです。
「一式」などざっくりした見積もりでは、トラブルが発生しても「その工程は見積もりに含まれていない」など言われてしまいかねません。
一方で詳細に項目を記載してくれる業者なら、どのような工事内容でどの建材を使用するのかが一目瞭然です。
そのためトラブルを未然に防ぐには、詳細に項目や数量が記載されている見積書を出してくれる業者を選択するのが適しています。
作業終了後は水を流してチェックする
雨樋工事が完了したら、引き渡しのタイミングで実際に水を流して機能を確認するのもおすすめです。
工事完了後は見た目がきれいになっているため、つい水が流れるかどうかの確認を忘れてしまいがちです。
万が一のトラブルを防ぐため、引き渡しの前後で雨樋から水が適切に流れるかどうか実際にチェックしてもらいましょう。
雨樋に関するよくある質問

雨樋に関して、多くの方が疑問に思うことをまとめました。
雨樋に関するよくある質問は以下のとおりです。
・雨樋の工事は足場が必要なの?
・雨樋のメンテナンスの時期って?
・雨樋は塗装した方が良いの?
それでは、1つずつ確認していきましょう。
雨樋の工事は足場が必要なの?
雨樋工事では必ずしも足場は必要ではありません。
足場費用は10~30万円かかるため、金銭的な負担を考慮して可能な限り足場は組まずハシゴや脚立で工事します。
ただし住宅の形状や雨樋の箇所、隣家との距離などによっては、足場の設置が必要となる場合もあります。
雨樋のメンテナンスの時期って?
雨樋は、取り付け後5~10年周期での点検が理想的です。
日常的に雨樋を遠くから眺めることで、不具合を早期に発見できる場合もあります。
メンテナンス周期に関わらず不具合が発生している場合は、できるだけ早く雨樋修理に対応している業者へ相談するのがおすすめです。
雨樋は塗装した方が良いの?
雨樋は、材質によって塗装の必要性が異なります。
硬質塩化ビニール製の雨樋は、塗装で耐久性が増すことはありません。
一方で板金性の雨樋は、定期的に塗装するのを推奨しています。
材質にかかわらず美観向上を目的とした場合は、雨樋を塗装するのがおすすめです。
雨樋に水がたまる前に定期的なメンテナンスがおすすめ

雨樋に水がたまることを放っておくとトラブルの元になります。
破損だけではなく、虫や異臭の発生など近隣にも迷惑をかける場合もあります。
定期的なメンテナンスは、雨樋に水がたまる問題を未然に防ぐために重要です。
雨樋の水たまりを予防することは、建物と居住環境の保護につながります。
「水たまりくらい」と思わず、業者までご相談ください。
雨樋専門リフォームパートナーでも雨樋の不具合に関する相談を受け付けていますので、ぜひこちらからお問い合わせください。
雨樋の修理に関する詳しい説明は、下記の記事でくわしく紹介しています。

内野 友和
この記事は私が書いています。
1979年生まれ。一級建築板金技能士。
父・内野国春の元で建築板金の修行を始め、2014年より代表となり家業を受け継ぐ。
20年以上、約5000件の現場経験で培った技術と知識で、建物の屋根・雨樋・板金・外壁工事を通じ、地域の皆様のお役に立てるように努力しております。