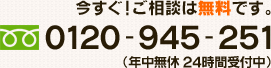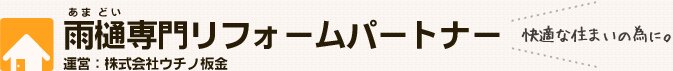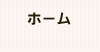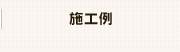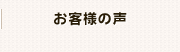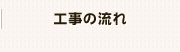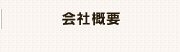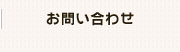雨樋とは?「とゆ」「とよ」との違いや修理費用、メンテナンス方法などを詳しく紹介

「雨樋について詳しく知っておきたい」
「雨樋をつける理由が知りたい」
雨樋の設置や修理を予定している場合に、このようにお考えになる方もいらっしゃるでしょう。
雨樋は普段あまり気に留めることがなく、どのような役割があるか詳しく知らないという方も多いかもしれません。
そこで、この記事では雨樋の基本情報について丁寧に解説していきます。
また、「とゆ」や「とよ」とはどう違うのか、設置するメリット・デメリットなども説明するので、より雨樋に関する知識を深められます。
ぜひ最後までご覧になってみてください。
雨樋とは

雨樋(あまどい・あまとい)とは、屋根の上に流れる雨水を軒樋で受けて、雨水を地上まで運ぶための装置です。
雨樋とは、主に以下のような部材で構成されています。
・軒樋
・軒継手
・軒曲がり
・集水器
・止まり
・呼び樋
・縦樋
・縦継手
・エルボ
・寄せマス
・角マス
さらに、軒樋や縦樋を固定するための金具があります。

雨樋と「とゆ」または「とよ」の違い

雨樋は、別に「とゆ」または「とよ」という読み方があります。
「とゆ」や「とよ」と書かれている看板を目にすることがあるかもしれませんが、意味は雨樋と同じです。
そのため、雨樋に関する施工依頼をする際は、業務内容に「とゆ」や「とよ」と書かれている業者にもお願いできます。
雨樋ってなんで必要なの?
雨樋は、住宅や人などに対しての被害を避けるために設置が必要です。
もし、雨樋を設置していない場合は以下のようなトラブルが発生しやすくなります。
・外壁が汚れる
・建物の基礎が傷む
・騒音が発生する
・通行人に迷惑をかける
屋根から勢いよく落ちてきた雨水が地面をえぐり、土や泥が跳ね返ることで外壁を汚したり、基礎を傷めたりします。
また、屋根から落ちる雨水が騒音を引き起こす可能性もあるでしょう。
さらに、建物の近くを歩いている人たちに屋根からの雨水がひどく飛び散ってしまうケースもあります。
このように、雨樋がなければさまざまな問題が発生するため、施工する必要があるのです。

雨樋を設置するメリットとデメリット
雨樋を設置するメリットがあれば、デメリットもあります。
メリットは、建物の外壁が汚れたり、騒音が発生したりするのを防ぐ点です。
デメリットは、雨樋のメンテナンスが必要だったり、人によっては美観が損なわれると思ってしまったりする点です。
雨樋が破損したら、排水機能を維持するために交換工事が必要になります。
また、雨樋内部にゴミや落ち葉などが溜まる前に掃除をしなければなりません。
このように、雨樋を設置することで雨によるトラブルが避けられるようになりますが、手間はかかることになるのです。

「軒樋」と「縦樋」のそれぞれの役割とは

雨樋の主要な部分に、「軒樋」と「縦樋」があります。
以下にて、それぞれの役割について紹介します。
軒樋と縦樋の役割を知っておくことで、より雨樋の仕組みが理解しやすくなるでしょう。
「軒樋」の役割
軒樋とは、屋根の軒先部分に設置される部材のことです。
屋根から流れてくる雨水を一番に受け止める部分となります。
軒樋には勾配がつけられており、傾斜があることで縦樋につながる「集水器」に雨水をうまく流せるのです。
「縦樋」の役割
縦樋とは、建物の外壁に沿って設置されている部材です。
軒樋から流れてきた雨水を地上に排水するための部分です。
縦樋と軒樋は集水器でつながっており、場所によっては縦樋には「エルボ」が使用されています。
エルボとは、縦樋の向きを変えるために施工される部材です。
美観をできるだけ損なわないように、縦樋がうまく外壁に沿って配置されるようにサポートしています。
雨樋に使用されている主な素材

住宅に設置する雨樋に使用されている素材は、主に以下の4つです。
・硬質塩化ビニール
・ステンレス
・銅
・ガルバリウム鋼板
以下にて、それぞれの素材で製造された雨樋の特徴について解説します。
雨樋の素材選びに悩まれている方は、ぜひ参考になさってみてください。
硬質塩化ビニール
硬質塩化ビニールとは、塩化ビニール樹脂を原料にした素材で、強度に優れています。
一般住宅でよく使用されているのが、この硬質塩化ビニール製の雨樋です。
ただし、紫外線に長い間さらされると劣化しやすいため、破損したら交換したり、定期的に塗装したりする必要があります。
ステンレス
ステンレス製の雨樋の大きな特徴は、サビが発生しにくいという点です。
ステンレスとは、一定量のクロムを鉄に加えて腐食しにくくした素材です。
クロムとは金属元素のことで、鉄に混ぜることで耐久性のある合金になります。
雨樋は雨にさらされ続ける部分なので、ステンレス製であれば美観を著しく損なうことはありません。
また、強度もあるため雨樋にも向いている素材といえます。
銅
銅製の雨樋はサビにくく軽量で、加工がしやすいという特徴があります。
耐久性に優れてはいますが、価格が高い点がデメリットとなります。
また、酸性雨によって傷みやすくなる点も注意が必要です。
酸性雨での影響が気になる方は、中心部にステンレスが使用されている、特殊加工された銅製の雨樋を選ぶのもおすすめです。
ガルバリウム鋼板
ガルバリウム鋼板は鋼板にメッキを施しており、耐久性が高いという特徴があります。
サビにくいですが、金属系の素材ではあるので、雨に長い間さらされる場合は注意が必要となります。
また、施工価格が高めになるので一般住宅の雨樋ではあまり使用されません。
価格ではなく、耐久性やサビにくさを求める方におすすめの素材です。
なお、雨樋の形を詳しく知りたい場合は「雨樋ってどんな種類があるの?素材や形状のパターンとそれぞれの特徴」もご覧ください。
雨樋に修理が必要となる主な症状と原因

雨樋に修理が必要となる主な症状には、雨水の溢れや破損、不具合などがあります。
以下にて、それぞれの症状の詳細と対策方法について解説します。
適切なタイミングで雨樋の修理ができるように、ぜひチェックしてみてください。
雨水の溢れ
雨樋から雨水が溢れ出ている場合は、不具合が発生しているので修理が必要となります。
雨水の溢れは軒樋や集水器の詰まりが原因である場合が多いため、まずは掃除をするようにしましょう。
DIYで行う際は、ホースで水を流しながらブラシを使ってこすり、排水がうまくできているのが確認できたら掃除の完了です。
しかし、高所作業は危険なので、専門業者に相談する方がおすすめです。
もしくは、軒樋の勾配がうまくつけられていない場合にも雨水が溢れてしまいます。
その際は補修が必要となるので、修理業者に依頼しましょう。
雨樋の破損や不具合
雨樋の破損や不具合があれば、排水機能が低下してしまうため修理が必要です。
主に、以下のような破損が見られたら早めに対処しましょう。
・ヒビ
・割れ
・歪み
・金具の外れや歪み
どれも、経年劣化や風雨による衝撃が原因で発生します。
場合によっては雨樋の全交換が必要なので、専門の業者に修理を依頼しましょう。
早めに対処することで被害の拡大を食い止めて、修理費用を抑えられる場合があります。
雨樋の修理にかかる費用相場

雨樋の修理費用の相場は、施工箇所や方法によって異なります。
例えば、部分補修を行う際に足場の設置が不要であれば、2~5万円ほどで施工可能です。
しかし、全体的に修理工事が必要な場合には15~30万円ほどかかります。
この工事価格に足場の設置費用は含まれていません。
もし、足場を設置する場合は10~30万円ほど追加で必要となるでしょう。
そのため、一般的な大きさの住宅の雨樋をすべて交換した場合は、足場費用を含めると40~60万円かかるケースが多いです。
雨樋の修理費用は意外にも高額なので、できるだけメンテナンスを行って、破損したり、劣化スピードを早めたりしないようにしたいところです。
以下にて、雨樋のメンテナンス方法を詳しくご紹介しましょう。
雨樋のメンテナンス方法

雨樋の排水機能を維持するためのメンテナンス方法を2つ紹介します。
主なメンテナンス方法は、定期的に点検をしたり、掃除を行ったりすることです。
以下にて、それぞれの方法の具体的な内容を解説しましょう。
雨樋の耐久性を維持するためにも、ぜひ確認してみてください。
定期的に点検を行う
雨樋が破損したり、不具合が起きたりしていないか、定期的に点検を行うようにしましょう。
少なくとも、5~10年に一度は点検を行うと安心です。
また、台風や大雪の際は雨樋が破損する可能性が高まります。
台風が過ぎ去ったり、積雪状況が落ち着いたりしたら、安全を確保しながら点検を行うことをおすすめします。
点検時には、雨樋の排水機能が正常かどうかを確認するために、集水器の反対側の軒樋から水を流してみるようにしましょう。
ただし、高所で点検が難しい場合は無理をせずに、業者に依頼するようにしましょう。
掃除を行う
雨樋はゴミや落ち葉などが詰まりやすいので、定期的に掃除を行い排水機能が維持されるようにしましょう。
雨樋の掃除は、少なくとも年に1~2回ほど行うとよいでしょう。
特に、住宅周辺に森や畑、公園などがある場合は雨樋にゴミや落ち葉が飛来しやすいので注意が必要です。
雨樋の大手メーカーをご紹介

単に「雨樋」といっても、メーカーや形状別にさまざまな商品があります。
形状としては、半月型や角型が主流です。
角型の方が受けられる雨の量が多いため、降水量が多い地域での住宅に適しています。
また、雨樋を販売している主なメーカーは以下の6社です。
・パナソニック
・積水化学工業
・タニタハウジングウェア
・デンカアステック
・タキロンシーアイ
・三菱ケミカルインフラテック
パナソニックでは、塩ビ樹脂の中にスチール芯をいれた「アイアンシリーズ」が人気です。
耐久性と強度に優れているため、雨や風による刺激を受けやすい雨樋部分におすすめの製品となります。
デンカアステックは、樹脂製で耐候性の高い雨樋の販売を行っています。
デザイン性にも優れているため、住宅の美観を損なわずに雨樋を設置できるのも嬉しいポイントです。
タニタハウジングウェアでは、ガルバリウム鋼板製やステンレス製を中心に、銅製の雨樋の製造・販売にも力を入れています。
特に、銅とステンレスのそれぞれの特性を活かして製造された「スーパー銅雨とい」は、高い耐候性を持つおすすめの雨樋です。
デンカアステックでもさまざまな素材の雨樋を製造・販売していますが、中でも樹脂製の商品に力を入れているメーカーです。
タキロンシーアイは、合成樹脂を使った製品を多く製造する大手のメーカーです。
強度や排水機能に優れた雨樋を製造しています。
さまざまな建築資材を取り扱う三菱ケミカルインフラテックからも、バリエーションが多数ある雨樋製品が販売されています。
多くの製品の中から、どのメーカーの雨樋を設置するか決めるのは難しいことでしょう。
施工業者に希望を伝えつつ、ご自宅に適した雨樋を選ぶようにしましょう。
雨樋は住宅を守る大切な部材!定期的にメンテナンスしよう

雨樋は雨による住宅への被害を防ぐための大切な部材です。
また、雨樋の耐用年数はおよそ20~30年なので、定期的にメンテナンスして寿命を維持しましょう。
ただし、高所での作業は転落事故が発生する危険があるため、不慣れな方は専門業者に依頼することをおすすめします。

内野 友和
この記事は私が書いています。
1979年生まれ。一級建築板金技能士。
父・内野国春の元で建築板金の修行を始め、2014年より代表となり家業を受け継ぐ。
20年以上、約5000件の現場経験で培った技術と知識で、建物の屋根・雨樋・板金・外壁工事を通じ、地域の皆様のお役に立てるように努力しております。